「飼う」と「買う」ーこれはどちらも、『かう』と読む同音異義語ですが、その意味や使い方には大きな違いがあります。特にペットに関する文脈では、どちらを使うかによって相手に伝わるニュアンスが変わってしまうことも。
この記事では、「飼う」と「買う」の違いを明確にし、使い方や例文を交えて、正しい使い分けをわかりやすく解説します。ペットとの暮らしを通じて「飼う」「買う」を学ぶメリットもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
「飼う」「買う」の違いを正しく理解しよう

「飼う」と「買う」は、同じ読み方でも意味や使い方が異なります。まずは、それぞれの言葉の意味の違いから確認し、日常生活での使い方にどんな違いがあるのかを見ていきましょう。
例文やよくある間違いを通じて、混同しがちなポイントをしっかり整理していきます。
「飼う」と「買う」の意味の違いとは?
「飼う」と「買う」は、どちらも日常的によく使われる言葉ですが、意味はまったく異なります。この2つの言葉の違いを正しく理解しておくことは、言葉を正確に使いこなす上でとても重要です。
まず、「飼う」という言葉は、生き物に対して使う動詞です。具体的には、動物やペットなどを世話しながら生活を共にすることを指します。例えば、「犬を飼う」「金魚を飼う」「鳥を飼う」といった使い方をします。このように、「飼う」には「面倒をみる」「育てる」といったニュアンスが含まれており、命ある存在との継続的な関係を意味しています。
一方で、「買う」は商品や物品、サービスに対してお金を支払って手に入れる行為を表します。例えば、「服を買う」「お菓子を買う」「チケットを買う」などのように、モノを対象にするのが一般的です。「買う」は経済的な取引を意味しており、金銭と引き換えに所有権を得る行為を示します。
つまり、「飼う」は生き物との関係性を含んだ行動であり、「買う」は物の取引に関する行動というように、対象と行為の本質がまったく異なるのです。これらを混同すると、文章や会話の中で不自然な表現になってしまうため、しっかりと違いをおさえておきましょう。
「飼う」と「買う」の使い方の違い
「飼う」と「買う」の意味がわかったところで、今度はその使い方の違いについて見ていきましょう。言葉は文脈によって微妙なニュアンスを持つため、使い方の違いを具体的に知ることはとても大切です。
まず、「飼う」の使い方には、対象が“生きている存在”であることが大前提となります。たとえば、「うさぎを飼う」「猫を飼う」「インコを飼う」といった形で、動物を自宅で世話しながら一緒に生活するという文脈で使われます。この言葉には、ただ所有するのではなく、「世話をしながら長期間にわたって共に暮らす」という継続的な意味合いが含まれている点が特徴です。
一方、「買う」はモノやサービスに対して使われます。「靴を買う」「本を買う」「ゲームを買う」などのように、商品を手に入れるときに用いられます。こちらは単発的な行動であり、「所有するために金銭を支払う」ことが主な意味です。
興味深いのは、「ペットを買う」という表現が間違いではないという点です。ペットショップなどで金銭を払ってペットを手に入れるという場面では「買う」という表現も成り立ちます。しかしその後、その動物の世話をし始めた時点で、「飼う」という行為に変わっていきます。つまり、「ペットを買って飼い始める」というように、両方の言葉が時系列的に使われることもあるのです。
このように、「飼う」と「買う」は、対象や状況によって自然な使い方が異なります。正しい使い方を意識することで、より丁寧で伝わりやすい日本語が使えるようになります。
「飼う」と「買う」はどう使い分ける?
「飼う」と「買う」は発音が似ているため混同されやすいですが、実際には使い分けがとても重要です。それぞれの言葉が持つ意味を正しく理解し、状況に応じて自然な日本語表現を選べるようになると、文章や会話における表現力が格段に向上します。
まず使い分けの基本として、「飼う」は生き物が対象です。「動物を飼う」「鳥を飼う」「魚を飼う」など、生活の中でその生き物の世話をしながら一緒に暮らすことを意味します。また、「飼う」は感情や責任を伴う行為でもあります。単に所有するのではなく、命ある存在を育てていくという意識が必要です。たとえば、「犬を飼う」という言い方には、日々の世話やしつけ、健康管理まで含めて、長期的に責任を持って接するという意味合いが込められています。
一方、「買う」はあらゆる「モノ」や「サービス」に対して使います。これは一時的な行為であり、お金を払って商品や権利を手に入れることを示します。「おもちゃを買う」「チケットを買う」「野菜を買う」などのように、対象は基本的に“無生物”です。ただし、例外としてペットショップでの購入時などには「ペットを買う」という表現も成立しますが、その後は「飼う」という行動に移行します。
このように、「飼う」と「買う」は以下のように使い分けると自然です:
- ペットショップで → 「ペットを買う」
- 自宅で一緒に暮らすようになってから → 「ペットを飼う」
つまり、「買う」は取得の瞬間、「飼う」は継続的な関わりを意味するのです。この違いを意識することで、場面に応じた適切な表現ができるようになります。
「飼う」と「買う」の使い方の例文
使い分けの理解をより深めるために、「飼う」と「買う」を実際の文章の中でどのように使うのか、例文を通して確認してみましょう。
【飼うの例文】
- 私は小さい頃から猫を飼っています。
- 弟が最近ハムスターを飼い始めました。
- 鳥を飼うには、毎日の掃除と餌やりが欠かせません。
- 実家では金魚を十匹以上飼っていました。
- 子どもが犬を飼いたいと言っているので、家族で相談中です。
これらの文に共通するのは、「飼う」が生き物を対象にしており、その生活の一部として関わることを表している点です。愛情や責任が伴う行為として自然に使われています。
【買うの例文】
- 新しい靴を買いに行きました。
- 本屋で話題の小説を買いました。
- スーパーで牛乳と卵を買ってきてください。
- 子どもに誕生日プレゼントを買ってあげた。
- 映画のチケットをオンラインで買った。
「買う」の例文では、対象がモノやサービスであることがはっきりしています。短時間で完結する“購入”の行為を中心にした表現です。
なお、両方の言葉が登場する例文もあります:
-
ペットショップで子犬を買って、自宅で飼い始めました。
このように、場面によって「買う」と「飼う」が連続して使われることもあります。どちらの行為も自然な形で表現することで、正確かつ伝わりやすい日本語を使うことができます。
「飼う」と「買う」の間違いやすいポイント
「飼う」と「買う」は発音が同じであり、漢字も似ているため、特に日本語学習者や小中学生にとっては非常に間違いやすい言葉のひとつです。意味は明確に異なるものの、文章の中で見分けにくいケースも多く、使い方を誤ると意味が通じなかったり、意図しない印象を与えることがあります。
最も典型的な間違いは、「生き物に対して“買う”を使ってしまう」ケースです。たとえば、「犬を買っています」という表現は、厳密には「犬を飼っています」が正解です。「買う」という言葉自体は間違いではないものの、この文では「所有」や「取引」のニュアンスが前面に出てしまい、感情や継続的な関係性を無視した冷たい印象を与えてしまいます。
また、文章を手書きで書く際に「飼う」と「買う」の漢字を混同してしまうケースもあります。漢字の部首やつくりの違いを意識しながら覚えることが大切です。「飼う」は「食べる(飠)」に関連しており、生き物を育てる行為に結びついています。一方「買う」は「貝」を含み、昔の貨幣を表しており、取引やお金に関係した意味を持ちます。
こうした違いを視覚・意味・用法の3つの観点から理解しておくと、誤用を防ぐことができます。また、文章作成の際には、文脈をよく確認して「対象は生き物か物か」「一時的な取引か継続的な関係か」という点を意識すると、自然に正しい言葉が選べるようになります。
「飼う」「買う」の実例とメリットで理解を深める

意味や使い方の違いを理解したあとは、実際の生活の中で「飼う」と「買う」がどう使われているのかを見ていきましょう。ペットを飼うという行為や、物を買うという日常的な行動を例に、さらに具体的なイメージを掴むことができます。
また、それぞれのメリットや教育的な観点からの考察も交え、より実践的に理解を深めていきます。
ペットを「飼う」とはどういうこと?
ペットを「飼う」という行為には、単なる所有を超えた意味が込められています。それは、「命ある存在と共に生きる」という覚悟と責任を伴うものです。可愛いから、癒されるからといった理由だけではなく、毎日の世話やしつけ、医療的なケアまで含めた生活全体の中で成り立つ関係が「飼う」ことの本質です。
例えば、犬や猫を飼う場合、毎日のエサやり、散歩、トイレの処理、病気になったときの治療など、多くの手間と費用がかかります。それでも人はペットを飼いたいと思うのは、そこに心のつながりや癒し、家族のような存在としての価値があるからです。
また、「飼う」ことには時間的な継続性もあります。数日や数週間ではなく、数年〜十数年にわたって共に生活していくことになるため、一時的な感情で決断するのではなく、将来的な見通しも含めてしっかりと考える必要があります。例えば、引っ越しや結婚、仕事の変化などによって飼い続けることが難しくなる場合もあるため、「本当にその命を守り抜けるか?」という視点は欠かせません。
さらに、子どもにとってペットを「飼う」ことは、命の尊さや責任感を学ぶ大切な機会にもなります。エサをあげる、水を取り替える、遊んであげるといった日常的な関わりを通して、思いやりや継続する力が自然と育まれていくのです。
このように、「飼う」という行為は単なる言葉ではなく、生活と心に根ざした深い意味を持つものです。その背景をしっかり理解してこそ、本当の意味でペットを「飼っている」と言えるのかもしれません。
物を「買う」とはどんな行為?
「買う」という行為は、日常生活の中で最も頻繁に行われる行動のひとつです。基本的には「お金を支払って物やサービスを手に入れること」を意味しますが、その背景には経済活動や欲求の充足、社会的なやりとりといったさまざまな要素が含まれています。
たとえば、スーパーで野菜を買う、書店で本を買う、ネットショップで洋服を買う——これらはいずれも「金銭と引き換えに物を所有する」という点で共通しています。この所有の目的は、自分の生活を便利にする、楽しむ、飾る、または他人への贈り物として使うなど多岐にわたります。
さらに「買う」は、物理的なモノだけに限らず、サービスや経験を得る場面でも使われます。たとえば「コンサートチケットを買う」「学習教材を買う」「美容室でサービスを買う」といったように、目に見えないものに対しても使える柔軟な表現です。
「買う」ことは、欲しいものを手に入れるという喜びだけでなく、自己表現や選択の自由とも結びついています。どのような商品を選ぶかによって、その人の価値観や生活スタイルが現れます。また、インターネットの発展により、世界中のあらゆる商品を簡単に「買う」ことができるようになった今、消費行動そのものが個人の生き方を反映するものにもなっています。
このように、「買う」という行為はただの取引にとどまらず、日常の中での選択や判断、そして社会との関わりを象徴する重要な行動なのです。
「飼う」「買う」のそれぞれのメリットとは
「「飼う」と「買う」は意味も対象も異なる言葉ですが、どちらの行為にもその特性に応じたメリットがあります。それぞれの立場から見て、どのような良さがあるのかを整理してみましょう。
まず「飼う」のメリットですが、これは主に心の豊かさに関係するものが多いです。ペットを飼うことで、癒しや安心感、孤独感の軽減、ストレスの緩和といった効果が得られます。特に高齢者や一人暮らしの方にとっては、ペットが心の支えとなり、生活に張り合いを与えてくれる存在になることもあります。また、日々の世話を通して責任感や思いやりの心が育まれる点も、大きな価値と言えるでしょう。
一方で「買う」のメリットは、生活の利便性と選択の自由に直結します。必要なものを自由に選んで手に入れることができ、生活を快適に整えることが可能になります。たとえば、季節に合った衣服を買うことで体調を整えたり、新しい家電を買って家事の負担を減らしたりと、現代社会における「買う」は、生活の質を高める手段でもあります。
また、ネットショッピングやキャッシュレス決済の普及により、「買う」という行為がより迅速かつ便利になったことで、時間の節約にもつながっています。自分に合った商品を見つけ、比較検討して購入するプロセスも、自己決定の喜びや達成感をもたらすひとつの体験です。
このように、「飼う」は心に働きかける行動、「買う」は生活を整える行動と捉えることができます。どちらも人生をより豊かにするための重要な選択であり、それぞれの目的や意味を理解したうえで行動することが大切です。
実生活での使い方のコツ
「飼う」と「買う」は日常生活の中で頻繁に登場する言葉ですが、使い方を間違えると相手に誤解を与えてしまうこともあります。正しく使うためのちょっとしたコツを押さえておくだけで、より自然で正確な日本語が身につきます。
まず大切なのは、「相手が生き物かどうか」をすぐに判断することです。対象が犬や猫、鳥などの動物である場合には「飼う」を使います。これは“命を育てる”というニュアンスがあるためです。逆に、対象が物やサービスであれば「買う」が適切です。どちらの言葉も文脈によって変わるため、迷ったときは文章の中で何について話しているのかを意識するだけで、自然と正しい表現が選べるようになります。
また、ペットの話をするときは特に注意が必要です。ペットショップで「買った」瞬間は「買う」が適していますが、その後は「飼っている」と表現します。例えば「ペットを買って、今は自宅で飼っています」というように、時系列に沿って両方の言葉を使うことでより正確な表現が可能になります。
実生活では、こうした微妙な使い分けを求められる場面が多いため、まずは会話や文章の中で違和感のない形を心がけることがポイントです。ニュース記事や本、SNS投稿などでも、プロがどのように言葉を選んでいるかを観察すると、自然な日本語の感覚が身についていきます。
子どもに教えたい「飼う」「買う」の違い
「飼う」と「買う」の違いは、大人にとっても紛らわしいことがありますが、子どもにとってはなおさら理解しづらいものです。しかし、この2つの言葉の違いを正しく教えることは、日本語教育においてとても大切なステップです。特に小学校低学年から中学年にかけては、言葉の意味や使い方を学ぶ重要な時期です。
教え方のコツは、身近な例や体験を通して伝えることです。たとえば、「おもちゃを買う」と「犬を飼う」というように、子どもが日常でよく接するものを例に挙げて説明すると、理解が深まります。また、実際にペットを飼っている家庭であれば、「このワンちゃんはどうしておうちにいるのかな?」「お店でお金を払って“買った”けど、いまは一緒に生活してるから“飼ってる”んだよ」という形で、具体的に教えるとより効果的です。
さらに、「飼う」は“お世話をすること”“命を育てること”だということを強調すると、子どもたちは責任感をもって言葉の重みを理解できます。一方で「買う」は“欲しいものを手に入れる”という行為であり、簡単に済む反面、物を大切にする気持ちも同時に育てることが大切です。
絵本や学習漫画などでも、「飼う」と「買う」をテーマにした内容があるので、そうした教材を活用するのもおすすめです。言葉の意味を知るだけでなく、正しく使えるようになることが目標です。子どものうちからこのような違いをしっかり理解することで、将来的にも言葉を大切に使えるようになります。
まとめ
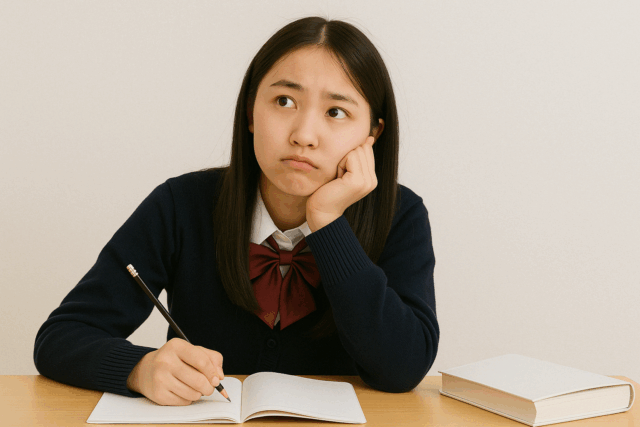
この記事のポイントをまとめます。
- 「飼う」は動物を世話しながら育てる行為を指す
- 「買う」はお金を払って物や動物を手に入れる行為を指す
- 同じ「かう」でも意味や使い方がまったく異なる
- ペットに関しては「買う」→「飼う」の順で使うと自然
- 「飼う」は責任や継続性が伴う行動として使われる
- 「買う」は単なる取引の行為として用いられる
- 実例や文脈に応じて適切に使い分けることが大切
- 子どもにも使い分けを教えることで語彙力や理解力が育つ
- ペットを飼うことには癒しや責任感などのメリットがある
- 間違いやすいポイントを知ることで正しい日本語表現が身につく
「飼う」と「買う」は、たった一文字の違いで意味が大きく異なる言葉です。特にペットに関する話題では、使い方を間違えると誤解を招くこともあるため、しっかりと使い分けを理解しておくことが大切です。
日常の中で自然に使いこなせるようになれば、日本語の表現力もグッと高まります。この記事が、あなたの語彙力向上や実践的な言葉の使い方の参考になれば幸いです。
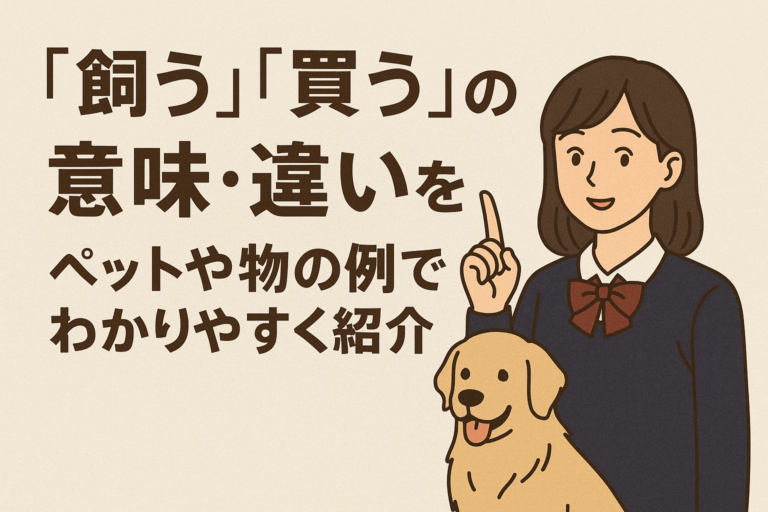


コメント